銀行融資リスケとは何か?基本的な仕組みと目的
リスケ(リ・スケジュール)とは、金融機関に対する借入金の返済条件(元金などの支払期日や金額など)を変更し、一時的に返済負担を軽減する措置を言います。
主に資金繰りが厳しくなった会社が金融機関に依頼し、元金返済の猶予や返済期間の延長をしてもらいます。その目的は、資金の流出を抑えて経営再建の時間を確保することにあります。
経験談:リスケが「延命措置」に終わる現実
私自身、これまで数多くのリスケ案件を担当してきました。その中で、リスケを実施した企業が、業績改善→リスケ終了→正常返済に至ったケースは、正直なところあまりありません。
リスケが決まった直後は、「これで会社の資金繰りが立て直せる」と社長も前向きな姿勢を見せます。
しかし、返済負担が軽減された安堵感から、当初立てた事業再建計画のことはすっかり置き去りにされ、忙しさに追われる日々を過ごすうちに、3ヶ月、半年と時間が経ってしまいます。
リスケの期限が近づくにつれ、社長の会話は「もう少し様子を見たい」「今は動けない」といった言葉に変わっていく。結局、再度リスケが繰り返され、気づけば3年、5年と元金返済がないままズルズルと延命を続けるケースもあります。
なぜリスケは業績改善につながらないのか?
リスケが形骸化する原因は、主に以下の3点にあります。
1. 明確な再建計画がないままリスケをしてしまう
「とりあえず資金繰りが楽になるから」との理由でリスケに踏み切り、肝心の収益改善策が曖昧なケースでは、返済猶予期間が過ぎても会社の業績になんの変化ももたらしません。
2. 経営者の危機感が薄れる
リスケによって元金返済が猶予されると、資金的なプレッシャーが一時的に緩みます。結果として、現状維持のまま「変わらない日常」が続いてしまうのです。
3. 外部支援を受けず、自力再建に固執する
中小企業の場合、第三者の目を入れることに抵抗感を持つ経営者も少なくありません。しかし、財務・経営面にメスを入れるには客観的な視点が不可欠です。
正常化に向けて本当に必要なこと
リスケを事業再建への「足がかり」にするためには、以下のようなアクションが不可欠です。
1. 実行可能な経営改善計画の策定
机上の空論ではなく、現実的な売上目標・コスト削減・事業再構築を数値化し、金融機関にも説明責任を果たす必要があります。
2. 経営者自身の覚悟と実行力
一時的な資金繰りの改善ではなく、根本的な構造改革に踏み出す覚悟が求められます。痛みを伴う判断を避けていては、何も変わりません。
3. 専門家との連携
中小企業診断士、公認会計士、経営コンサルタントなど、外部の知見を取り入れた再建チームを作ることが回復への近道になります。
銀行員の視点から伝えたいこと
リスケはあくまで「時間を買う」ための手段であり、目的ではありません。銀行は、リスケを通じて企業再生を期待していますが、それには「経営者の行動の変化」が不可欠です。
逆に言えば、事業計画が曖昧なままリスケを申し出ても、結局は信頼を失い、次の支援を得ることも難しくなってしまいます。
リスケが企業の未来を閉ざすのではなく、次のステージへの準備期間になるよう、正しい認識と行動が求められています。

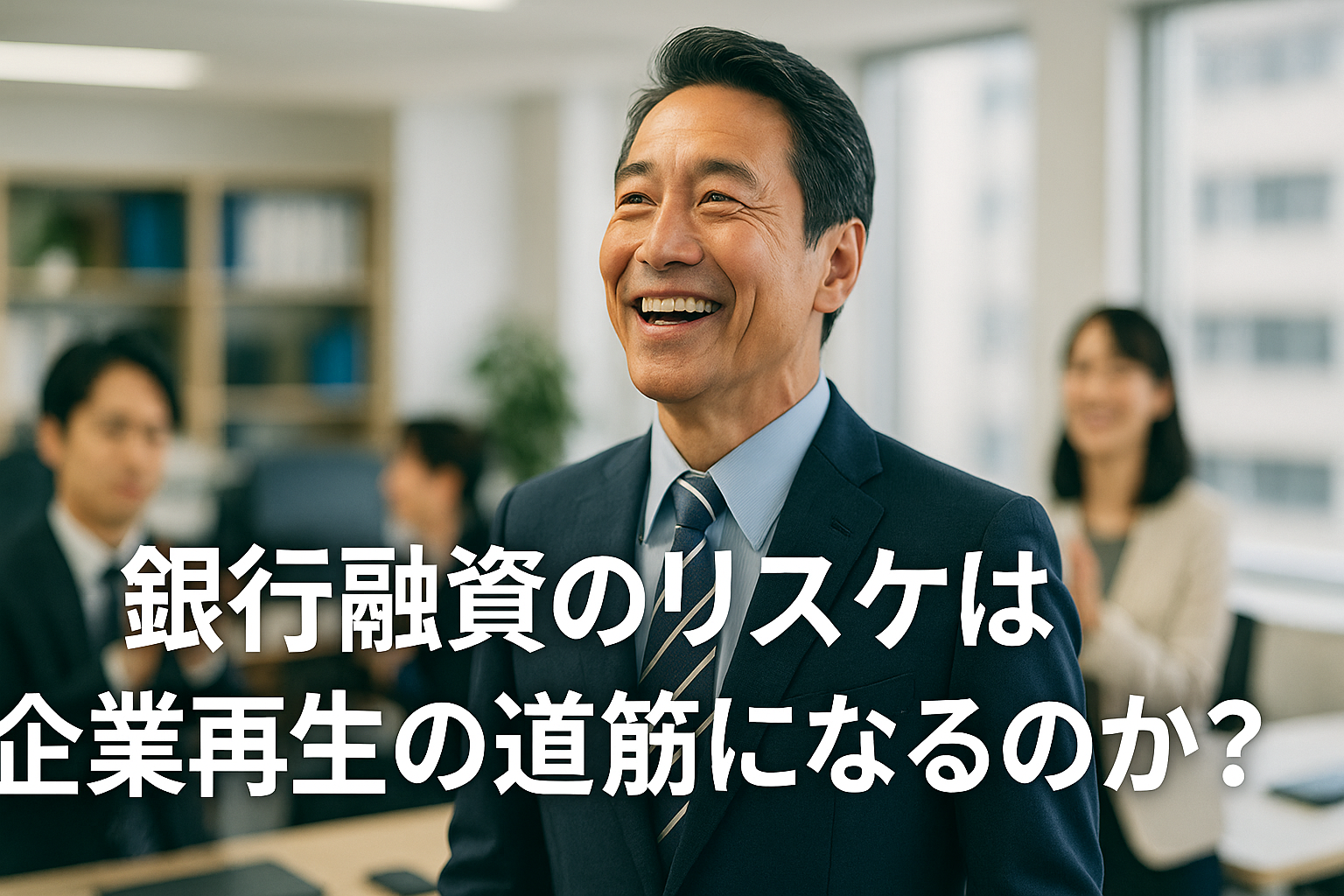
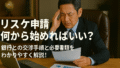

コメント