こんにちは。
ワタナベミエです。
今回は銀行の本部出身者が現場の支店長として成功するのか? という内容を掘り下げて解説します。
本部で優秀だった人が支店長になって成功するとは限らない…
支店業務の経験が乏しいまま現場に立たされ、戸惑いながら日々の運営に苦労する。そんなケースも珍しくないのが銀行のリアルです。
銀行の本部と支店とでは役割が大きく異なります。本部は戦略立案やリスク管理などの『全体統制』を行う一方、支店はお客さまと向き合い、預金や融資、支店の人材マネジメントなど『現場の実行部隊』として機能します。
同じ銀行内部でも、その仕事の進め方、判断のスピード、人材の動かし方には驚くほどのギャップがあります。
このため、本部で優秀な実績を上げていた人ほど、「支店長」としての現場対応に戸惑うことがあるのです。
本記事では、
❒ なぜ本部出身者が支店で苦戦するのか
❒ 支店長として求められる視点とは何か
❒ 組織として、どのようなサポートが有効か
といった点を、支店の現場で働く立場から解説していきます。
「本部から支店へ」という異動の意味と、その成功条件をあらためて考えるきっかけになれば幸いです。
はじめに:銀行における本部と支店の違い
銀行の組織は大きく分けて「本部」と「支店」の二層構造になっています。
本部は、経営戦略、審査・リスク管理、制度設計などを担う“全体を統制する中枢”です。
一方、支店は営業や窓口を通じてお客さまと直接向き合い、融資や預金、投資の提案など日々の業務を回す“現場の最前線”。
同じ銀行にいても、
✅ 使用するシステム
✅ 決裁のスピード
✅ 顧客対応への感覚
が全く異なるため、異動した際にギャップを感じるのは当然といえます。
本部で優秀だった人が支店長になって苦戦する理由
本部で活躍してきた人が支店に異動すると、「あれ?」と感じる瞬間が少なくありません。
その主な理由は以下の通りです。
支店業務の経験不足
長年本部にいると、現場で何が行われているかを肌で感じる機会がほとんどなくなります。スピード感と柔軟性の違い
本部はルール遵守やリスク回避を重視しますが、支店は目の前の顧客ニーズに即応する柔軟さとスピードが求められます。部下とのコミュニケーション
支店では若手行員や事務職、パート従業員などと日常的に連携しなければならず、様々な立場の人とコミュニケーションをとる必要があります。
本部でのロジカルな判断力や調整力があっても、現場では“人間関係とスピード”が鍵を握るのです。
支店業務のブランクがもたらすギャップ
支店業務を数年離れるだけでも、状況は大きく変わります。
📌 融資稟議のシステムが刷新されている
📌 稟議の運用方法が変わっている
📌 事務処理が事務センターなどへ集中されている
📌 顧客のニーズや取扱商品も変化している
支店長がこうした変化に戸惑ってしまうと、現場の動きを止めてしまうケースもあります。
本部の経験者が「自分が一番わかっている」といった様子で振る舞ってしまうと、部下からの信頼を得にくくなるリスクもあります。
支店長として現場に立つことの意味とは?
とはいえ、こうした異動には組織としての「狙い」があることも事実です。
それは、本部だけで完結せず、現場感覚を持ったマネジメント層を育てることです。
支店長として現場に立つことで、
💡 数字へのプレッシャーに強くなる
💡 お客さまとの信頼関係の重みを再認識する
💡 部下の育成と支援の難しさを体感する
このようなことをリアルに体験すると、本部では得られない“現場目線”を身につけることができます。
どうすれば「本部経験者の支店長」は成功するのか?
本部出身者が支店長として成果を出すためには、次のようなポイントが鍵になります。
本人のアクション
✅ まず現場を「観察する」姿勢を持つこと
今までのやり方を周りに押しつけず、既存のオペレーションを理解するところから始める。
✅ 頼れる人材を活用すること
事務のベテランや営業経験豊富な中堅に相談しながら、徐々に自分の色を出していく。
✅ 本部と支店との“仲介役”になること
現場の声を本部に届けるパイプ役として機能すれば、信頼も高まり相乗効果が生まれます。
組織として有効なサポート策
✅ 支店業務の再教育プログラムの整備
事務処理のシステムや稟議フローなど最新情報をキャッチアップできる研修制度の導入
✅ 適応プロセスも人事評価に反映する
数値目標だけでなく、現場との関係構築のプロセスも評価対象にし支店運営の質を重視する
✅ 支店長間のネットワークの構築
同じ立場で悩みを共有できるコミュニティを作ることで、孤立を防ぎ、ノウハウが交換できる
まとめ:求められるのは“両方の視点”
本部と支店、どちらか一方に偏った経験では、銀行全体のマネジメントは難しい時代になっています。
だからこそ、両方の立場を経験し、バランスよく“視野”を持てる人材が求められているのだと思います。
本部からの異動に戸惑う支店長も、現場との信頼関係を築ければ大きな成果につながりますし、支店側の人間も柔軟にその経験を活かせる雰囲気づくりが必要です。
人事異動は“修行”ではなく“学び”のチャンス。
組織と個人の双方にとって、実りある時間にできるかどうかは、お互いの歩み寄りと理解にかかっています。

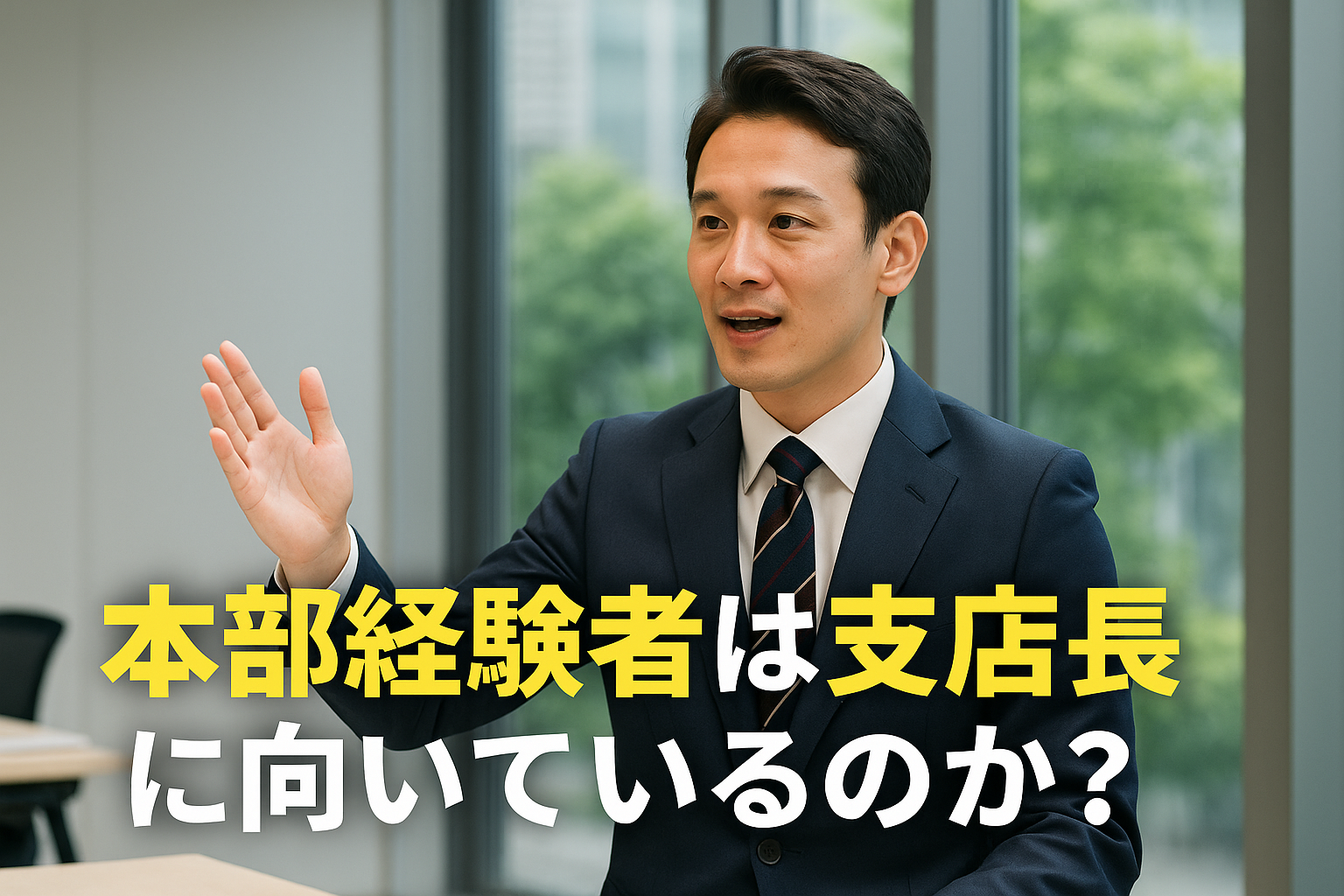
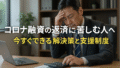
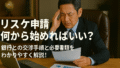
コメント