こんにちは。
ワタナベミエです。
今回の記事は「なんとかなる思考」で融資を申し込む経営者の方たちに伝えたい内容です。
「返済のあてもないのに、借りればなんとかなる――。」
そんな安易な考えで融資に頼る経営者がいるのが、銀行の実態です。
しかし、その思考は企業を破綻に導く危険な入り口です。
本記事では、銀行の現場で実際に見た「返済の見通しもなく融資を求める経営者」の心理や行動パターン、そしてその末路までを具体的に解説。
加えて、“借入依存”から脱却するための実践的な対策も紹介します。
忙しいあなたにこそ知っておいてほしい、経営と資金繰りのリアルをまとめました。
結論:「借りれば何とかなる」は最も危険な思考
銀行員として日々多くの経営者と向き合っていますが、「返すあてもないのに借りようとする」経営者には共通する危険な思考があります。それが「借りれば何とかなる」という根拠のない楽観主義。これは企業経営において、最も致命的な落とし穴です。
経営者がこの思考に陥る理由とは?
この思考に陥る背景には、いくつかの心理があります。
- 過去の成功体験への執着:「あの時もうまく乗り切れたから、今回も大丈夫だろう」と思い込みやすい
- 現実逃避:資金繰りに追われ、冷静に現状分析ができなくなっている
- プライドの高さ:「倒産=経営者としての敗北」と考え、意地でも事業を継続しようとする
- 助言への拒否反応:税理士や銀行員からの現実的なアドバイスに耳を貸さない
こうした心理状態では、借入金があたかも「資金調達の万能薬」のように思えてしまいます。
銀行員が見抜く「返済の見込みがない融資申し込み」
銀行側は、融資の相談に来た時点で「この融資は危険だな」と感じ取るポイントがあります。
- 資金使途があいまい(例:「とりあえず運転資金を借りたい」)
- 返済計画に現実味がない(「半年後にはなんとかなる」など曖昧な予測)
- 利益を出しても既存借入の返済に追われて、資金繰りに余裕がない
- 粉飾決算の兆候が見られる(異常な在庫増加や売上の急増)
表面的な書類の整合性より、「話の筋が通っているか」「再建への具体的行動があるか」が重要なのです。
こうした社長に共通する行動パターン
- 売上よりも融資のことばかり考えている
- 現場や数字の分析を後回しにする
- 「お金さえ入れば全部解決する」という発言が多い
- 資金繰り表を作っておらず、どんぶり勘定
- 助成金や補助金ばかりに期待を寄せる
これは「経営」ではなく、もはや「延命」です。銀行はそこを冷静に見ています。
「借りれば何とかなる」思考から脱却するために
✅ 結論:お金の問題は、お金では解決しない
「借りれば何とかなる」という考えは、一見すると前向きなように見えますが、実は現状から目をそらし、問題の本質に蓋をしているだけです。
この思考を続ける限り、資金繰りに追われ続け、経営の自由はどんどん失われていきます。
脱却の第一歩は、「お金を借りる前に、一旦立ち止まって」です。
🔍 問題提起:なぜ「借りれば何とかなる」と思ってしまうのか?
この思考に陥る背景には、いくつかの心理的要因があります。
- 過去に“なんとかなった”経験の記憶(成功体験の呪縛)
- 現実を直視することへの恐怖や不安
- 外部からの「借りればいいじゃないか」という助言
- 売上や利益ではなく、「資金調達=借入」の経営が常態化している
そして、何より「今をしのぐこと」が目的になってしまうと、本来の経営判断力が鈍っていきます。
💡 具体策:その思考からどう脱却するか?
数字と向き合う
まずはキャッシュフローを見える化し、「売上」「経費」「借入返済」「手元資金」を整理します。
資金繰り表を作成するだけでも、事業の実態が見えてきます。
借りる理由と返す根拠を明確にする
借入を「埋め合わせ」ではなく、「将来の利益創出のための投資」として考え直しましょう。
借りる=延命ではなく、再建の一手にする必要があります。
相談相手を変える
「借りればいい」としか言わない相手からは距離を取りましょう。
銀行員・会計士・中小企業診断士など、現実を見た上で一緒に考えてくれる専門家に相談することが鍵です。
売上と利益に意識を戻す
借入で「時間を買った」ら、その時間を使って「売上をつくる」「利益を出す」行動にフォーカスしてください。
借りたお金の返済は、結局のところ“利益”からしか生まれません。
🧭 まとめ:自分自身の経営に、再び“主導権”を
「借りれば何とかなる」ではなく、「何とかする力を自分でつける」。
それが経営者としての責任であり、真の成長への道です。
借入は“目的”ではなく“手段”です。
その思考を変えるだけで、経営判断の質は確実に変わります。
最後に:資金調達は「最後の手段」ではなく「成長の手段」
「借りればなんとかなる」と思っている経営者の多くは、本質的な問題解決を後回しにしています。借入による資金調達は“時間を買う”手段であって、“問題を解決する魔法”ではありません。
銀行員として伝えたいのは、「借入は企業の将来に対する投資」であり、「その未来に現実味がなければ、融資は逆効果になる」ということです。
経営者の皆さんには、「お金を借りる前に、立ち止まって考える力」を持っていただきたいと、心から願っています。


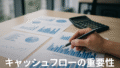

コメント