こんにちは。
ワタナベミエです。
経営者の皆さんは、ご自分の会社はどのくらいまで借入ができるのかと考えたことはありますか?
適正な借入額はどのくらいなのかを表す指標に「借入比率」があります。
借入比率には総資産に対する借入比率、売上高に対する借入比率などがありますが、銀行では取引先の借入額が「月商(1か月における企業や事業の売上高のこと)の何ヵ月分に相当するか」を見て、その会社の借入額が一般的に多いのか少ないのかを判断します。
一般的な業種ごとの目安としては以下のように考えられます。
業種ごとの一般的な借入比率の目安
製造業・小売業
製造業や小売業は月商の2~4か月分程度
製造業や小売業は、在庫や設備投資が必要なため、一定の借入は許容されます。ただし、過剰な借入が利益を圧迫しないよう、返済可能な範囲に抑えることが重要です。
飲食業
飲食業は月商の3か月分程度が目安
飲食業は、初期投資(内装工事や厨房機器の購入)が多い一方、現金商売なので日々のキャッシュフローが比較的安定しやすく、返済計画をしっかり立てることが求められます。
サービス業
サービス業は月商の3~4か月分程度
サービス業は一般的に在庫を抱える必要はありませんが、労働集約型のため人件費や家賃などの固定費が高く、売上減少時に借入に依存しやすい傾向にあります。
借入比率が高いとどんなリスクがあるのか?
一般的に借入比率が月商の6か月分を超えると、以下のリスクが生じやすくなります。
返済負担が重くなる
月々の返済額が利益より多くなることで、手元の現預金で返済しなければならなくなり、資金繰りが厳しくなる恐れがあります。
こうなると、借入金の返済のために、また銀行から借りるといった悪循環に陥る可能性もあります。
追加融資が難しくなる
既存の借入が多いと、追加融資の審査で不利になることもあります。
借入過多の状態では、少しでも売上が低迷すると返済不能に陥る可能性が高くなるためです。
経営の柔軟性が低下する
資金不足により、緊急時の対応や事業拡大の余地が狭まる。
借りられる時に、借りられるだけ借りておきたという経営者の方もいらっしゃいますが、借入の適正水準を超えると、成長投資のための融資が通らないこともあり、せっかくのチャンスを逃すことにもなるのでご注意ください。
借入の適正比率を見極めるポイント
業界の標準を把握する
同業他社の借入比率を参考にする。
キャッシュフローを重視する
利益だけでなく、手元に残る現金が十分であるかを確認する。
借入金の用途を明確にする
運転資金、設備資金、成長投資など、目的に応じて適正額を検討する。
融資を受ける前に確認すること
月々の返済額
一般的には月商の10~20%以内に収まることが理想的ですが、これはあくまでも目安であり、利益率の高い業種(例: IT・ソフトウェア業界)は売上の15~20%程度でも返済が可能な場合があります。
一方で利益率の低い業種(例:卸売業・小売業 )は売上の5~10%程度に抑える方が安全と言えます。
自己資金とのバランス
自己資金が多いほど、借入比率を低く抑えられますが、一方であまり自己資金を投入すると、万が一、銀行から融資を受けることができなかった時に、資金繰りに困ることがあります。
一般的に自己資金の比率は20%程度が目安と言われています。
余裕を持った事業計画を作成する
売上が計画を下回る場合でも返済が滞らないように、売上計画の7割程度の売上でも返済できるような資金計画を組むのが理想的です。
まとめ
一般的には、借入比率は月商の3か月分程度が目安とされ、6か月分を超えると危険水域とみなされます。
ただし、業種や事業規模、経営状況によって適正水準は異なるため、自社のキャッシュフローや収益構造をよく分析することが重要です。
また、銀行担当者と相談し、無理のない借入計画を立てることで、安定した経営を実現しましょう。

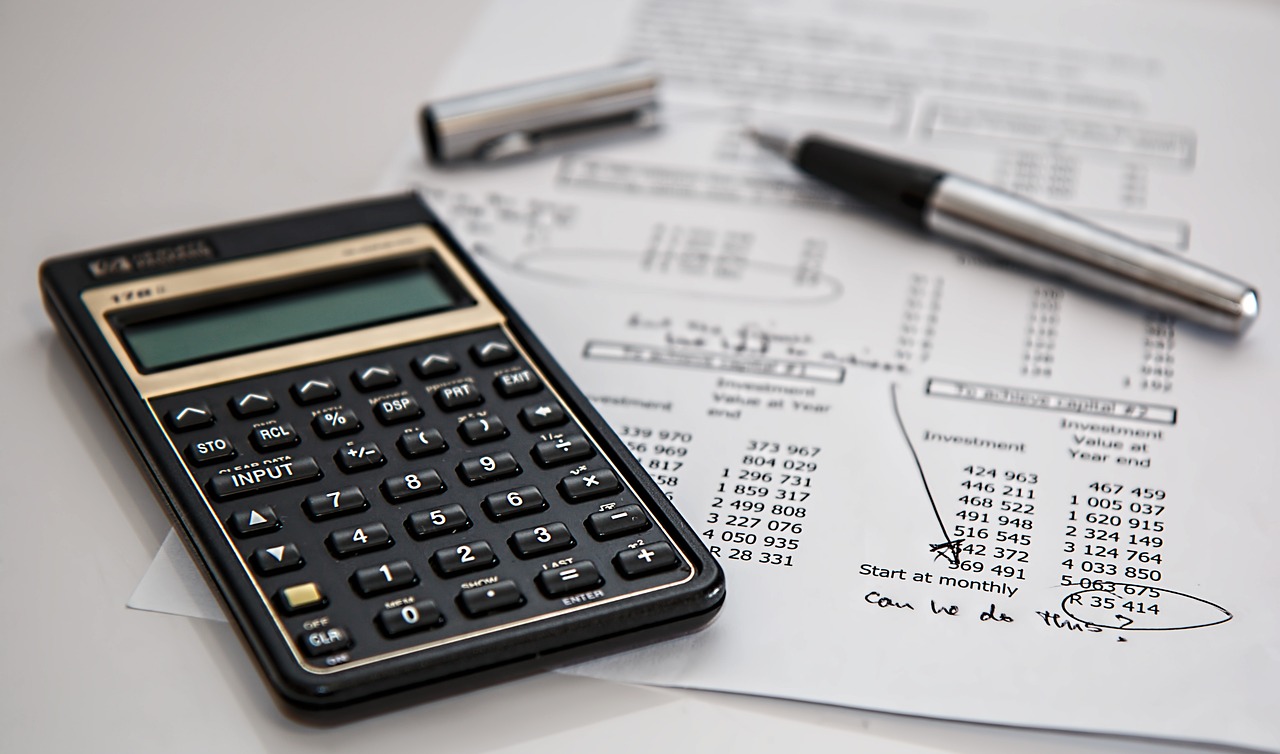


コメント